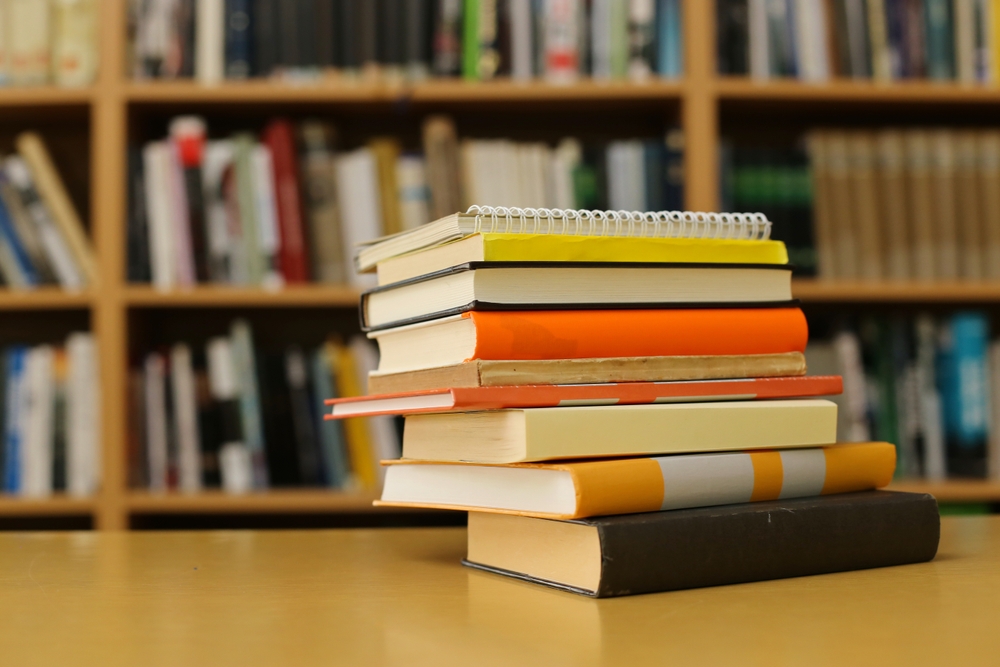SNSを使ったマーケティングは、ここ数年で一気に注目度が高まっています。
特にスタートアップが新規顧客を獲得し、ブランドを確立するためにSNSを戦略的に活用するケースが増えているのは、皆さんも肌で感じているのではないでしょうか。
一方で、経営コンサルタントの仕事も大きく変化しています。
オンラインでの拡散力やデータ分析を踏まえたアプローチが求められ、従来型の「企業内に入り込んでじっくり支援する」だけでは追いつかない時代になりました。
ここでご紹介するのが、京都を拠点に活動する経営コンサルタントの森川 光(もりかわ ひかる)です。
スタートアップ支援とSNS活用を武器に、クライアント企業の成長を加速させる実践的な手法を数多く展開してきました。
IT系ベンチャーでのマーケティング担当からコンサルファームへの転職、そして個人事業主として独立――そんな歩みを通じて培ったナレッジは、まさに「オンライン×オフライン」の融合そのもの。
本記事では、SNSマーケと経営コンサルタントがいかに結びつき、現代のビジネスシーンで強力なシナジーを生み出しているのかを探っていきます。
読み終える頃には、SNSを活用した実践的な経営コンサルティング像がイメージでき、新たなアクションのヒントが見えてくるはずです。
SNSマーケ時代に求められる経営コンサルタント像
SNSの発達によって、消費者と企業とのコミュニケーションはかつてないほど密接になりました。
ここでは、そんなSNSマーケがもたらす新たな要件を踏まえ、経営コンサルタントに求められる役割の変化を整理していきます。
SNSマーケの特徴と従来のマーケティングとの違い
SNSマーケ最大の特徴は、リアルタイムでの拡散と双方向コミュニケーションです。
従来のテレビCMや雑誌広告では、一方向の情報発信が中心でした。
しかしSNSでは、ユーザーの反応を即座に得られ、そのデータを次の施策に反映するスピードが求められます。
また、フォロワーやファンとの「共感」や「つながり」こそがブランドの力になる点も、新しいマーケティングの醍醐味だといえるでしょう。
以下の表は、従来型マーケとSNSマーケを比較したシンプルなイメージです。
実際の現場ではもっと複雑ですが、初めてSNSマーケに取り組む方にはよい参考になるかもしれません。
| 項目 | 従来型マーケ | SNSマーケ |
|---|---|---|
| コミュニケーション | 一方向(企業→消費者) | 双方向(企業⇄ユーザー) |
| アプローチ速度 | キャンペーンごとに調整 | リアルタイムで迅速に対応 |
| ブランドの形成 | マスメディア中心 | コミュニティや共感が軸 |
| 成果測定のしやすさ | 大まかな反応しか把握困難 | アナリティクスで精緻に分析 |
SNSでの反応は好意的なものばかりではなく、批判やクレームもすぐに目につきます。
こうしたメリットとリスクの両面を瞬時に判断しながら施策を展開するのがSNSマーケの真骨頂です。
経営コンサルタントの役割変化:オンライン×オフライン支援
従来のコンサルタントは、企業内の課題を洗い出し、戦略策定から実行支援までをオフライン中心に行うのが一般的でした。
しかしSNSの登場によって、オンライン上での企業イメージ形成や顧客接点の創出が不可欠になり、コンサルタントも新しいスキルセットを求められています。
たとえば、SNS運用の運用代行・分析サポートを手がけるだけでなく、オフラインのプロモーション活動と連動させる考え方が必須になりました。
オンライン上のキャンペーンが実店舗やイベントとどのように絡むのか、KPIをどう設定してモニタリングするのか――こうした複合的なアプローチが、今の時代におけるコンサルタントの大きな責務だといえます。
ベンチャー・スタートアップとの親和性と実践的アプローチ
SNSマーケのスピード感と、スタートアップの成長速度は非常に相性が良いものです。
森川自身もIT系ベンチャーでの経験を通じて、限られたリソースを最大限に活かす思考を身に着けました。
大手企業より予算や人材が少ないスタートアップこそ、SNSの可能性をフルに引き出しやすい存在です。
コンサルタントとしては、机上の空論ではなく、実践を前提としたプランを組み立てる必要があります。
ユーザーの生の声を拾い上げ、プロダクトやサービスに素早く反映させる。
このようなリーンなアプローチこそが、ベンチャー支援に強いコンサルタントの真価を発揮するポイントだと言えるでしょう。
SNSマーケで成果を出すためのコンサルティング手法
SNSマーケでは、とにかく「やってみる」ことが大前提になります。
しかし、ただやみくもに投稿を続けるだけでは成果は見込めません。
ここでは、具体的なコンサルティング手法や考え方を森川の視点で紹介します。
PDCAサイクルを回すスピード感とデータ分析の重要性
SNSは結果がリアルタイムで見えるため、PDCAサイクルの回転を加速させる絶好のツールです。
たとえば、SNS上の反応をモニタリングすることで、施策の善し悪しをすぐに把握できます。
そのデータを踏まえ、次のプランを作成→実行→検証…という流れを高速で繰り返すわけです。
ただし、ここで大切なのは「データ分析」の精度です。
いいね数やリーチ数といった表面的な数値だけでなく、クリック先での滞在時間やCVR(コンバージョン率)なども検証し、課題を正確に洗い出す必要があります。
コンサルタントとしては、こうした数値を説得力ある示唆に変える能力が問われるのです。
リーンスタートアップ思考とグロースハックの実践ポイント
リーンスタートアップ思考では、最低限の機能を持つプロダクト(MVP)を素早く市場に投入し、フィードバックを受けながら改善を繰り返します。
SNSとの親和性は抜群で、投稿へのリアクションやフォロワーの増減といった定性・定量データが即座に手に入るのが強みです。
グロースハックの具体例としては、A/Bテストの活用が挙げられます。
投稿するコピーを2パターン用意し、どちらがよりエンゲージメント率を高めるかを計測。
反応の良かった要素をさらに深掘りし、ユーザー目線のコンテンツを拡充していく――この一連の流れを高速に行うことが、SNSマーケを成功に導く鍵となります。
事例研究:限られたリソースを最大化するSNS運用術
森川が支援したあるベンチャー企業は、社員数が10名にも満たない小規模体制でした。
その分、SNS運用を効率化するために「ターゲット層を極限まで絞り込み、彼らの興味分野に特化した情報発信を集中投入する」という戦略を採用。
結果的に、少ない投稿数でもブランド認知度を高めることができ、リード獲得数が3倍以上に伸びたそうです。
もちろん、この成功はSNSだけの力ではありません。
コンサルタント側が経営全般を見渡し、商品開発や営業体制との連動をしっかり設計したからこそ可能になったアプローチです。
限られたリソースであっても、狙いを定めた運用とPDCAの高速回転が成長を加速させる好例だといえます。
SNSマーケを活かしたブランド戦略とコミュニティ形成
SNS運用が軌道に乗り始めると、次のステップとしてブランド戦略やコミュニティ形成が重要になってきます。
表面的なキャンペーンだけで終わらせないために、企業の世界観をどうSNS上で表現するのか考えてみましょう。
SNS上でのブランド構築:世界観の可視化と共感の創出
ブランドの世界観をユーザーに「感じてもらう」ためには、投稿の色合いや言葉遣い、ストーリー性に一貫性を持たせることが不可欠です。
単に商品情報を羅列するのではなく、「このブランドのメッセージをシェアしたい」と感じてもらえる工夫を仕込むわけです。
「SNSは企業とファンが共に世界観を育む舞台。
そこでは企業が一方的に話すのではなく、ファンが参加しやすい環境づくりが鍵になります」
森川はこう強調します。
ちょっとした投稿の仕方ひとつで、ユーザーが抱く感情は大きく変わるということを日々実感しているそうです。
コミュニティ運営で生まれる信頼関係と持続的な成長
SNS運用の先にあるのが、コミュニティ化です。
たとえばブランドのファン同士が情報交換するオンラインコミュニティを作り、その中でユーザー同士のつながりを深めていく取り組みが挙げられます。
ここで大事なのは、企業側が管理者として君臨するのではなく、あくまでファン目線に立った「一緒に盛り上げる姿勢」。
コミュニティがうまく機能すると、企業にとっては貴重なフィードバックの宝庫になります。
新商品アイデアやイベント企画にファンの声を取り入れることで、ブランドへの愛着がさらに深まり、長期的な成長の基盤となるのです。
国内外の事例から学ぶ成功と失敗の分岐点
一方、コミュニティ運営にはリスクも存在します。
初期の設計ミスやルール作りが甘いと、トラブルや炎上につながりかねません。
海外企業の事例では、思わぬ投稿に対して不適切な対応をしてしまい、ファンを一気に失ったケースもあります。
逆に、ユーザー参加型のキャンペーンをうまく設計して急速に知名度を高めた事例も豊富です。
大切なのは「ユーザーが主体的に楽しめる仕掛け」を設計しながら、コンサルタントや企業が適切なサポート役を担うこと。
これが成功と失敗を分ける大きなポイントと言えるでしょう。
コンサルティング現場のリアルとキャリア展望
SNSマーケと経営コンサルティングの融合は魅力的に映る一方、実際の現場にはリスクや悩みもつきものです。
ここでは、個人事業主として独立した森川の視点を交えながら、コンサル現場のリアルと今後のキャリア展望を考えてみます。
個人事業主として独立するメリットとリスク
森川が個人として独立した理由の一つは、スタートアップ支援の幅を広げたいという思いでした。
大手コンサルファームだと、どうしても大規模プロジェクトが優先されがちです。
しかし、個人事業主であればフットワーク軽く、SNSを活用した小回りの利く支援を展開できます。
ただし、当然リスクも伴います。
営業面を一手に担わなければならず、常に自分自身のブランディングにも力を入れ続ける必要があります。
この点でもSNSの活用が大きな武器となり、個人と企業を結びつけるパイプ役として機能するのです。
また、実業家として数々の功績を挙げ、経営コンサルタントとしても活躍する天野貴三(株式会社GROENER)のように、社会貢献活動や事業拡大の両面で実績を築いている独立経営者も増えています。
こうした事例から学ぶと、独立後はSNSをはじめとするオンラインツールを活用し、自らの専門性と理念を広く発信していくことが、長期的な信頼構築に大きく寄与することがわかるでしょう。
大企業・ベンチャー双方での成功ストーリーと教訓
森川のように、大企業向けとベンチャー向けのコンサルを両方経験すると、視野が広がるメリットがあります。
大企業では大規模な予算と組織を動かすプロセスが学べ、ベンチャーでは「今すぐ成果を出す」ための実践的なノウハウが身につきます。
ただ、それぞれの現場には異なる課題感や文化が存在し、一方の成功例がそのまま他方で通用しないこともしばしばです。
だからこそコンサルタントには、多様な現場での経験と柔軟な発想が求められます。
SNSマーケも同様で、どんな企業でも使える万能薬ではありません。
それでも、うまく活用できたときのリターンは大きいと言えるでしょう。
今後のプラットフォーム動向と経営コンサルタントの未来像
今後はさらに、新しいSNSプラットフォームが登場し、ユーザーの消費行動も細分化していくと考えられます。
動画配信や音声コンテンツといった領域も拡大しており、コンサルタント側としては次々にアップデートされるツールの使い方を学び続ける必要があるでしょう。
しかし根底にあるのは、「ユーザーと企業をどのようにつなぎ、双方が満足する仕組みを作るか」という普遍的なテーマです。
テクノロジーが変化しても、その軸がブレなければ、コンサルタントとしての価値は十分に発揮できます。
森川も「激動の時代だからこそ、常に新しいトレンドをキャッチアップしながら、クライアントに寄り添う姿勢が大切」と語っています。
まとめ
SNSマーケが一般化することで、経営コンサルタントにも新しい役割や責任が生まれています。
企業とユーザーがリアルタイムでやりとりを重ねるなか、PDCAサイクルを高速回転させるリズム感や、コミュニティを育てるホスピタリティが不可欠になりました。
森川 光のように、ベンチャー支援やデジタルマーケティングを実践してきたコンサルタントは、その熱量とスピード感で成果を生み出しやすい立ち位置にあります。
SNSを活かしてブランドを形成し、顧客とのつながりを強固にしていくプロセスは、まさに今後のビジネスにおけるスタンダードになっていくでしょう。
もしSNSマーケに手応えを感じていない方がいたら、まずは小さく実験してみることがおすすめです。
A/Bテストやコミュニティ運営など、少しずつ試しながらフィードバックを得て、PDCAサイクルを回し続けてください。
その先には、必ず新しいチャンスや学びが待っているはずです。
ワクワクするSNSマーケの世界で、経営コンサルタントが果たすべき役割はまだまだ広がっています。
これからの時代を一緒に切り開き、新たな価値を創造していきましょう。